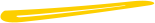COLUMN 01

30年来の友人が語る、今も変わらないシンゾウ
興梠慎三と初めてFWでコンビを組んだのは、おそらく山下圭介さんだろう。
サッカーをはじめた大宮サッカースポーツ少年団(宮崎県)で、興梠はサッカーの楽しさを知る。
そこで出会った30年来の友人が語る興梠慎三とは——。
プロになっても、浦和レッズの選手になっても、学生時代と変わらない姿に、興梠の人としての魅力はある。
浦和レッズのオフィシャルサイトにある興梠慎三のプロフィールを見ると、チーム歴の最初に「宮崎東サッカースポーツ少年団」(宮崎東SSS)とある。
「1学年上には鹿島アントラーズでもチームメートだった伊野波雅彦さんがいて、1学年下には川崎フロンターレなどでプレーした久木野聡がいた。メンバーもそろっていたのでチームはかなり強くて、全国大会に出場するなど、本当にいい経験をさせてもらいました。練習はかなり厳しかったですけど、そこでサッカーについて、さまざまなことを教わりました」
しかし、興梠にはチーム歴に載っていない原点がある。
大宮サッカースポーツ少年団(大宮SSS)——。
宮崎東SSSでサッカーの奥深さや厳しさを知ったなら、大宮SSSではサッカーの魅力、楽しさを知り、そして向上心を抱いた。
サッカーとの出会いについては、母・興梠定子さんの言葉を借りよう。
幼かった息子が風を切って、土のグラウンドを駆ける姿を思い出しながら言った。
「短距離も、長距離も、とにかく走るのが速かったんです。あとは小さいときからどんな球技をやらせても、ボールを扱うのが得意でした」
3歳年上の兄の影響から、小学生になると野球を初めたが、定子さんは疑問を抱いていた。
「もっと、慎三に合うスポーツがあるのではないか」
知人から近くにサッカークラブがあることを聞いたのは、そんなときだった。
息子を連れて見学に行くと、グラウンドで子どもたちが走り回っていた。
「そのとき、これだって思ったんですよね。サッカーなら息子の足の速さが活かせるんじゃないかって」
サッカーは息子の能力や特長に合っている。瞬間的にそう感じたが、定子さんが大切にしたのは息子の意志だった。
隣にいる息子に聞いた。
「サッカーやってみる?」
「うん。やってみたい」
興梠がサッカーとの邂逅を紐解く。
「大宮SSSは、練習も週2回あるくらいで、決して強いといえるチームではなかった。でも、僕は、ここでサッカーが楽しいスポーツだということを知ったし、教わりました」
そして、大宮SSSで興梠は30年来の付き合いとなる友人に出会った。
「最初は、サッカーをする仲間だったのが、家も近かったから、そこから常に一緒に遊ぶようになって。お互いの家にもよく泊まりに行っていましたね。
中学生になってからは学区が違うので、別々の学校に通っていたのに、なぜか彼も僕の友だちと一緒に遊ぶことが多かったくらい」
 当時を懐かしむ山下圭介さん
当時を懐かしむ山下圭介さん
おそらく、興梠がそのキャリアにおいて、初めて2トップを組んだのが山下圭介さんだろう。
山下さんも記憶を辿ってくれた。
「シンゾウとは2トップでプレーする機会も多かったんですけど、ゴールを決めるのは、ほとんどシンゾウでした。野球をやっているのも知っていて、ピッチャーで4番だったと思います。スポーツも遊びも、何をやっても一番で、苦手なのはきっと水泳くらいですよね(笑)。一番身近に、シンゾウといううまい選手がいたので、自然と自分も、練習も、試合も一生懸命にやりたいなって思っていました。それくらい刺激をもらう存在でした。出会ったころはまだ、野球もサッカーもどっちつかずで、サッカーに全体重を乗せているような感じじゃなかったから、練習の日以外に遊ぶことも多くて。本格的にサッカーにのめり込みはじめたのは、大宮SSSから宮崎東SSSに移ってプレーするようになってからだったと思います」
遊んでいても負けん気の強さは感じていた。
「当時、プロレスも流行っていたので、技の掛け合いをしていたんですけど、僕が技を掛けたら、自分も技を掛け返さないと気がすまないようなヤツでした。だから、僕が掛けたら、次はシンゾウ。シンゾウが掛けたら、次は僕。その延長線上で喧嘩が始まるみたいな(笑)。プロレスだけでなく、トランプでもそう。自分が勝たないと、とにかく気がすまない。こんな負けず嫌いなヤツがいるのかって思っていました」
 宮崎東SSS時代の興梠(後列一番右)
宮崎東SSS時代の興梠(後列一番右)
宮崎東SSSでプレーするようになってからの興梠は、サッカーの練習や試合で忙しくなったというが、2人の付き合いは続いたし、変わらなかった。
中学校も別々ならば、高校も別々。思春期を迎えても、青年になっても、2人は小さいときのまま、ずっと「シンゾウとケイスケ」だった。
「高校受験に落ちたと聞いたときも、心配していました。そのあと、サッカーを続けるなら、鵬翔高校に入学できるという話を聞いたときも、サッカーができて、高校にも通えるなら、それはそれでシンゾウにとってはいいことだなって思っていました」
言葉にせずとも、友人として陰ながら心配し、そして興梠のことを思っていた。
「ただ、プロのサッカー選手になるとは思ってなかったですけどね。鵬翔高校から鹿島アントラーズに加入した1学年先輩に当たる増田誓志君のことは、シンゾウからも周りからも、よく話を聞いていましたけど、真面目でストイック。そういう人が、プロサッカー選手になると思っていたので。どちらかといえばシンゾウは真逆ですよね。だから、プロになるって聞いたときは、思わず『えー!』って驚きました。でも、誓志君を追うように鹿島アントラーズを選んで、最初の身体測定かなにかで、外国人選手よりも足が速かったという報道を見て、『確かにな』って思うところもありました。一緒にボールを蹴っていたときから、確かにあいつは足が速かったし、秀でているところがあったなって」
プロサッカー選手になっても、地元・宮崎に帰ってくると、いつもと変わらないシンゾウだった。
「おそらく18歳でプロサッカー選手になると、鼻が伸びてしまう人も、少なからずいると思うんですよね。でも、シンゾウはプロサッカー選手になっても、鹿島アントラーズで試合に出るようになっても、浦和レッズに移籍しても変わらなかった。独身時代はオフがあったら、ふらっと宮崎に帰ってきて、迎えに行くと、スーパー銭湯に行きたいって言うんですよ。『スーパー銭湯でいいの?』って、こっちが聞き返すくらい。名前も知られてきていただけに、こっちのほうが気を遣いますよね。それでもシンゾウは、微塵もそんな雰囲気を出さないんですよね。活躍してから出会った地元の人に対しても、たとえ顔と名前が一致していなかったとしても、分け隔てなく接している。地元で暮らしていたときと、ずーっと変わらないんですよね」
その人柄こそが、これまでプレーしてきたチームメートに好かれ、愛されてきたゆえんだろう。
ただ、それは興梠にとっても、同じだったのだろう。
興梠が地元を思い出しながら、つぶやいた。
「ケイスケもサッカーが好きなので、結局、サッカーの話になるんですけどね。『この間の試合はダメだったね』『あのゴールはナイスだったね』。毎回、試合を見てくれて、そのたびに連絡をくれる。昔と変わらない感じがまた、うれしくってね。大人になって出会った友だちではなく、小さいときから過ごしてきた友だちは、一緒に辛い時期を過ごしたり、一緒に悔しい思いをしたりしてきたので、時間が経っても、どこか分かり合えている感じがあるんですよね。それが今も一緒にいて、心地いいというのが一番にある」
 2013加入会見時の興梠慎三
2013加入会見時の興梠慎三
山下さんが興梠の覚悟を感じたのが、鹿島アントラーズから浦和レッズへの移籍を決めた2013年だった。
興梠に移籍の理由を尋ねると、珍しく濁されたという。
「ほら、浦和レッズってビッグクラブだろ。だからお金だよ、お金」
笑ってごまかす横顔に、決意を感じ取っていた。言葉でいくら軽口を叩いていても、幼いころから苦楽をともにしてきた友人は見抜いていた。
「純粋にすごいヤツだなって思いました。アントラーズでリーグ3連覇を成し遂げて、試合にもコンスタントに出場して活躍していた。ミシャさん(ミハイロ ペトロヴィッチ監督)が作り上げたサッカーをしてみたいという話も聞いていましたけど、ある意味、ポジションが約束されているような環境を捨ててでも、自分がやりたいことを優先したんだろうなってことはわかって。20代ということもあって、照れ隠しから茶化していましたけど、リスクを冒してでも、自分がやりたいことを貫こうとする姿勢はすごく格好いいなって思いました。同時に、シンゾウらしいなとも……」
友人として鹿島アントラーズ、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌で駆け抜けた20年間を見届けてきた。
「少し前から、ここが痛い、あそこが痛いという話も聞いていたし、ボソッと『もう無理かもしれないな』って言葉も聞いていたので、頑張っているなと思って見ていましたけど。僕自身は、感謝の気持ちが大きいですね。シンゾウのおかげで、僕自身もいろいろなものを見せてもらいました。だから、あと1年、もう1年やってくれという気持ちは抱かなかった。シンゾウのプレーをまだまだ見たいですけど、この20年間で十分すぎるくらいに見せてもらったと思っています」

歩みも違えば、職種も違う。だが、山下さんにとって、興梠はずっと「シンゾウ」であり、一番近くにいる目標でもあった。
ファン・サポーターが興梠のプレーやゴールに活力をもらっていたように、彼もまた勇気をもらっていた。
その思いから発した「感謝」という言葉だった。
「ただ……欲を言えば、もう1回、ゴールを決めるところをみたいなとは思いますね」
それは30年来の友人であるケイスケから、選手であるシンゾウへのラストメッセージだ。
(文・原田大輔)
COLUMN 02

チームのため、仲間のために走る原点はあのころに
あのとき、あの言葉、あの行動がなかったら、今の興梠慎三はいないと断言できる。
多感な青春時代を過ごしていた彼に食らいつき、向き合った人がいる。
当時・鵬翔高校サッカー部の監督を務めていた松崎博美さんだ。
恩師の存在なくして、埼玉スタジアムで躍動する背番号30はいなかった。
寝顔を見ながら、興梠慎三は思い出していた。
「この人がいなかったら、間違いなく今の自分はいなかっただろうな」
ある年のことだ。
鵬翔高校サッカー部の監督を務めていた松崎博美さんは病気を患い、東京都内で手術を受けた。
そのことを聞きつけた興梠は、1人で病室を訪ねた。
部屋の扉を開けると、恩師は静かに眠っていた。椅子に腰掛けた興梠は、起こすのでもなく、恩師の顔をずっと眺めていた。
「自分にサッカーの楽しさを再認識させてくれたのはこの人だったし、本当にサッカーが好きな人だよな。早く元気になって、また子どもたちを指導してほしいな。それで全国に羽ばたくようなチームや選手を育ててほしいな」
同時に20年近くになる恩師との日々も駆け巡っていた。
しばらくして松崎さんは目を覚ますと、目の前に教え子がいることに驚いた。
「ずっと、そこにいたのか? 起こしてくれればよかったのに」
「術後だし、眠っていたので起こしませんでした」
興梠を高校の3年間、指導した松崎さんは言う。
「手術することも、心配させまいと、本人には言っていなかったのに、誰かから聞いたんでしょうね。事前に来るとも言わずに、目を開けたら慎三が座っていて、私の顔を見ているものだから、それはもうビックリしました。わざわざお見舞いに駆けつけてくれたんですから。昔から彼は、そうした人懐っこさというか、温かさを持っていたんですよね」
小学生のときから、大会に出ては得点王になったり、優秀選手に選ばれたりと、たびたび名前の挙がる「興梠慎三」の存在は知っていた。
宮崎市立大宮東中学校では、専門的な指導者がいなかったこともあり、厳しい練習や必要な技術を教わる機会がなかったことも知っていた。
それでも松崎さんは、中学3年の大会が終わったあとには、興梠に声を掛け、月1回開いていた練習会に参加してもらった。
「スピードもあるし、ドリブルもうまかった。何より、ボールタッチが柔らかかったんですよね。スピードを生かしながら、しっかりとボールを扱うことができていたので、これは将来性のある選手だなと思って見ていました。その練習会には、宮崎市外の選手も参加していたのですが、そうした選手たちからも、慎三は一目置かれる存在でした」
その子が他校の入試に落ちて、高校の行く当てがなくなっていると知ったのは、それからしばらく経ってからだった。
松崎さんは、学校側に掛け合い、興梠の入学を相談。当初学校側はすんなりとは認めてくれなかったが、最終的に松崎さんの情熱が実り、サッカー部に入ることを前提に進学できることになった。
しかし、入学して間もなく、興梠は「サッカー部を辞めたい」と、弱音をこぼすようになった。その背景を松崎さんは、こう明かす。
「おそらく、おもしろくなかったんでしょうね。当時は、県のトレセンに選ばれているような選手が、特待生として入学してくれていました。その特待生たちは、入学前から遠征に参加してもらっていたり、練習試合に出場してもらったりしていました。チーム内における選手たちのバランスを図る必要もあったし、お互いに伸ばしていかないといけないところもあったので、当然、特待生でもない慎三だけを優先するわけにはいかなかった。だから、試合にも出られず、いわゆるレギュラー組で練習もできない状況、環境に、サッカーがおもしろくなかったんだと思います」
興梠も深くうなずく。
「特待生たちは小学生のときに、相手チームで対戦してきた選手たちばかり。その選手たちが、トップチームで練習し、試合にも出場していた。自分としては、その選手たちよりも、自分のほうが絶対にうまいと思っていたから、そうした状況がもどかしかったんですよね。おまけに鵬翔高校は、中学以上に上下関係も厳しくて、そういうすべてに疲れたというか、嫌気が差してしまった」
練習もサボるようになり、サッカーを辞めたいとこぼす興梠を、松崎さんは何度も、何度も呼び出した。
「サッカーを辞めたら、もったいないぞ。実力があることは知っている。頑張ったらプロになれるかもしれないんだから頑張ってみよう」
「いや、俺はもういいです。サッカーはもうやりたくありません」
別の日には職員室、また別の日には常駐する技術室に呼び出して、膝を突き合わせて話をした。
「まだ、気持ちは変わらないのか?」
「監督、もういいですって。俺はもうサッカーはやりたくないんですよ」
「頑張ったら、将来的に日本代表にもなれる可能性があると思うんだけどな」
松崎さんが根気強く向き合ったから、今の興梠はある。
恩師が当時を回想する。
「他の生徒に言って、職員室や技術室に来るようにと言うと、やっぱり話をしに来るんですよ。確かに慎三は少しやんちゃなところはあったかもしれないですけど、他の子どもたちは『はい』とか『いいえ』とかくらいしか言えない時期でも、慎三はいろいろなことを聞いてきたり、話してくれたりする、会話が成立する子どもでした。だから、話せば伝わることや思いをわかってくれるとも感じていました。呼べば、必ず話をしに来たように、そうした義理人情にあついところが、卒業後も付き合いが続いてきたところだと思いますし、いろいろなことに対して、責任感が強い男でしたから」
考えた松崎さんは、心変わりのきっかけになればと、遠征につれていき、試合に出場させた。すると、かすかだが、サッカーへの情熱に再び火がついたのがわかった。
若気の至り。照れくさそうに、興梠は当時を振り返った。
「話をしにいっていたのは、自分が高校に通うためには、サッカーを続けることが前提だったからなんですけどね。監督のところに行かなかったら、高校もやめなければならない事態になる。毎回、呼び出されるのは、面倒くさかったですけど、話を聞いてもらって、自分の気持ちをわかってもらえたらいいなという思いもありました。それでも、松崎監督は、自分に何度も、何度もこう食らいついて、説得してくれたので、本当に感謝しかないですね」
 恩師と過ごした鵬翔高校グラウンド
恩師と過ごした鵬翔高校グラウンド
サッカーへの情熱を取り戻しはじめた興梠に、松崎さんはさらに火を点す方法を考えた。
1学年上で、早くから際立つ存在だった増田誓志を、興梠の練習相手に指名したのである。
「誓志に言って、慎三と一緒に練習するように言いました。慎三は負けず嫌いですからね。誓志は小学生のときから有名で、中学時代も県内でナンバーワンと言われていた選手。Jリーグのスカウトたちもよく見に来てくれる存在だったので、その選手と組まして一緒に練習をすれば、慎三は先輩を先輩と思わないタイプだったから、追い抜いてやるっていうくらいの負けん気の強さが出てくるかなと」
興梠は「全然、(その意図には)気づかなかった。いいようにコントロールされていたんですね」と笑ったが、見事に増田を意識した興梠は、成長を遂げていった。
松崎さんが当時の姿を振り返る。
「最初はBチームで練習したり、Bチームの試合に出ていましたけど、そこで点を取ったりしてAチームに入りました。そのAチームでも結果を残しはじめて。そのあたりから、サッカーが少しおもしろくなってきているのはわかりました」
興梠のサッカーに対する意欲、姿勢を強烈に感じたのが、2年生で迎えたインターハイ(全国高等学校総合体育大会)だった。鵬翔高校は、増田や興梠の活躍もあって全国大会で勝ち進んでいく。迎えた準々決勝では愛知県の東邦高校と対戦し、2-2で試合を終えると、PK戦の末に1-3で敗戦した。
「勝てばベスト4入りという試合に負けて、慎三は涙を流しながら悔しがっていました。そのとき、彼は本当に一生懸命サッカーに取り組んでいるんだなって。誓志は本当に練習の虫で、いつも1人で残ってボールを蹴っているような選手でした。でも、逆に慎三はチームの練習が終わったら、まずグラウンドにいることはない。当時からオンとオフがはっきりしている選手でした」
2年連続で全国高校サッカー選手権大会に出場すると、3年時の第83回大会では準々決勝に進出した。U-18日本代表にも選ばれるなど、頭角を見せると、先輩である増田を追うようにして、2005年に鹿島アントラーズでプロのキャリアをスタートさせた。
「誓志は早くから鹿島に絞っていましたけど、慎三は正直、他のチームも候補としてはありながらも、最終的に本人が鹿島に行くことを決めました。今思うと、プロサッカー選手としての基礎を、鹿島で学んだこともよかったと思っています。特に、決める前に相談されるようなことはなかったですけど、いろいろなクラブの人から話を聞いて、自分自身で決断したのではないかと思います」
プロへの一歩を踏み出すときは、改まって相談はなかったというが、その後は節目、節目で相談や連絡があった。
人生の岐路に食らいついてくれた恩師に、背中を押してもらいたいという思いがあったのだろう。
それは2013年に浦和レッズへの移籍を決めるときも——。
「8年間プレーしたので、鹿島への恩や義理は果たせましたよね」
「もう返せたんじゃないか。お前がやりたいところでプレーしたらいいじゃないか」
2016年にオーバーエイジ枠(OA)で、リオデジャネイロオリンピックに出場するときも連絡があった。
松崎さんは「本人は意志を固めていたとは思うんですけど」と、やり取りを明かす。
「OAとしてオリンピックのメンバーに声を掛けてもらっているのですが、断ろうかと思っているんです」
「せっかくのオリンピックという舞台なんだから、悩むことはないだろう。行ってきたらどうだ」
宮崎市内にある生目台公園には、松崎さんが発起人となり建てられたという、リオデジャネイロオリンピック出場を記念した石碑が建っている。
 興梠慎三、そして松崎氏の名前が刻まれた宮崎市内の石碑
興梠慎三、そして松崎氏の名前が刻まれた宮崎市内の石碑
「オリンピックで1点取ったけど、グループステージで敗退して。試合を終えてすぐに連絡があったんです。『どこにいるんだ』って聞いたら『ブラジルです』と。それで『何日に帰るので、一緒に食事できますか?』って。それでスーツケースを持ったまま、宮崎に帰ってきたんです。日本代表のユニフォームにサインを入れて渡してくれて。そういう地元を愛する心や熱い一面がありました」
のちに本人が燃え尽きたと明かしたリオデジャネイロオリンピックを終え、慣れ親しんだ地元に帰り、恩師の顔を見たかったのだろう。
浦和レッズで、2度のアジア制覇を筆頭に、5つのタイトルを獲得した。浦和レッズで記録したリーグでのゴールは114得点を数え、J1リーグ通算168得点は歴代2位の得点数である。
「こんなにね、成功するというか。すごい選手になるとはね。9年連続で2桁得点ですか。しかも、J1リーグで18年連続ゴールという記録を打ち立てるなど、浦和レッズの顔になったことが、何よりうれしいですよね」
 比類なき記録を残してきた興梠慎三
比類なき記録を残してきた興梠慎三
多感な高校3年間はもちろんのこと、今日まで見守ってきた松崎さんに、興梠の魅力を聞いた。恩師から返ってきたのは、プレーではなく人柄だった。
「人間性ですよね。プレー面も、スピードや点を取るタイミングとか、たくさん魅力はありますが、やっぱり一つ挙げると人間性になる。誰に対しても、分け隔てなく接することができるあの性格が魅力でしょうね」
浦和レッズで出会ったミハイロ ペトロヴィッチ監督が、興梠にとってサッカー界の「父」ならば、松崎さんは間違いなく「師」だという。
「あの人がいなければ、間違いなく今の自分はいないですからね。本当に頭が上がらないです」
一つ道が逸れていたら、一つ道を踏み外していたら、サッカーをやめていただろう。そうなれば、浦和レッズがアジアの頂点に立つことも、我々が背番号30のゴールに歓喜し、酔いしれることもなかったかもしれない……。
自分が歩いてきた確かな足跡を振り返り、噛み締めながら興梠は言った。
「簡単な言葉になりますが、一つ言えるとすれば、高校3年間で、僕は改めてサッカーの楽しさを教わりました。あとは何だろう……。サッカーはチームスポーツなので、自分だけというわけにはいかないじゃないですか。周りもうまく見ながら、うまく活かしながらプレーする。それまでは自分だけがよければいいといった思いでやっていたけど、高校時代にはチームのためにプレーすることをすごく培った感じはあります」

思い起こせば、浦和レッズのユニフォームをまとい走る背番号30の姿も、プレーも、いつもチームのことを考えていた。チームのために、チームメートのために、そしてチームの勝利のために——その原点は、苦しみもがいた高校3年間にあった。
(文・原田大輔)
COLUMN 03

興梠慎三が追いかけた母の背中
興梠慎三の母・定子(さだこ)さんは息子について「産んだだけ」「勝手に育った」と言う。
だが、サッカーとの出会いをつくったのも母なら、背中を押してくれたのも母だった。
その母の目に息子・慎三の歩みはどのように映っていたのか。
2024年7月31日、埼玉スタジアム——。
プロサッカー選手として歩んだ20年のうち、半分以上となる11年を過ごしたホームで、引退発表会見に臨んだ興梠慎三は言った。
「今日は自分の誕生日です。自分にとってもこの日は特別な日ですけど、自分は母に一番感謝しないといけない。そして母に感謝するべき日だと思っています。僕がここまで現役を続けられたのも、母が丈夫な身体で産んでくれたことが一番だと思っています」
 自身の誕生日に引退発表をした興梠
自身の誕生日に引退発表をした興梠
そう息子が母への感謝を伝えれば、会見の模様を画面越しに見ていた母・定子さんは、凛々しい息子の姿と言葉に感謝した。
「私が言ったら周りに笑われるかもしれませんが、慎三については本当に面倒を見ていないんです。仕事でいろいろなところに行くたびに、みんなに『どうやって育てたんですか』と聞かれるのですが、『勝手に育ちました』と答えています。私はもう産んだだけ。それくらい手のかからない子でした。
会見でも、お弁当を作ってくれたり、送り迎えをしてくれたりとかではなく、『丈夫に産んでくれて』と言っていましたよね。本当にそのとおりで。丈夫に産んだことを、こんなに喜んでくれる子がいるのかなって……」
定子さんは「だから」と言葉を続ける。
「慎三は勝手に育ったんです。むしろ、周りや世の中に育ててもらったと思っています」
興梠は1986年7月31日、第三子として宮崎県宮崎市に生まれた。
物心がつき、覚えているのは、いつも仕事で忙しく飛び回っている母の姿だった。
興梠本人も「母の言っているとおりなんですよ」と笑う。
「自分がサッカーをはじめた小学生のときから、他の選手の親は(自分の子どもの面倒を見るのに)熱心で、試合があったら毎回のように応援に駆けつけていました。父兄がやる仕事もあったので、それをみんなの親がやっていた。でも、自分の親は仕事が忙しくて、全く来なかった。小さいながらに周りからどう思われているのかなって、少し気になっていた時期もありました。
だけど、結局は自分がサッカーを楽しむことが大切で、自分がどれだけチームのためにいいプレーができるかが重要だと思って。そこに親が来る、来ないは関係ないと思っていました」
ただ、定子さんも「何もしていない」と笑うが、しっかりと息子を導いていた。なぜなら、息子をサッカーと出会わせたのは、他でもない母だったからだ。
「とにかく足が速かったので、足の速さを生かせる競技がいいのではないかと思って、最初に(地元宮崎市の)大宮サッカースポーツ少年団に連れて行ったんです。そこで、やっぱり足が速いし、ボールの扱いもうまいと言われたんです。ただ当時は、野球とサッカーの両方を習っていて、どっちも本格的にやっているわけではなかった。私は本人の意志が大切だと思っていたので、慎三にはすべて、自分で決めさせてきた。だから、このときもサッカーと野球のどっちを選ぶかと聞いたら、慎三は『サッカー』と言ったんです」
 自らサッカーの道を選んだ興梠慎三
自らサッカーの道を選んだ興梠慎三
サッカーとのタッチポイントを創出しただけでなく、自分で決断させているところに、親としての導きがあった。
そして、本人がサッカーを選んだのであれば、その可能性を広げたのもまた、母だった。定子さんは、知人から近くに強豪チームがあることを聞くと、練習見学に連れて行った。
そして、ここでも母は、ちゃんと息子に決断させていた。
宮崎東サッカースポーツ少年団(宮崎東SSS)の練習を見た興梠が言った。
「ここはレベルが高いし、チームも強いから、自分は試合に出られないと思う」
「じゃあ、どうするの? やめておく?」
「レギュラーにはなれないかもしれないけど、ここで頑張ってみる」
定子さんは言う。
「それで宮崎東SSSに入ってから、グーッと伸びたんですよね。成長したのはチームの指導もあったと思いますけど、親が決めたのではなく、自分で決断したことが大きかったと思っています」
興梠が高校生になると、定子さんはさらに仕事で忙しくなり、家を空ける機会も増えた。
練習や試合、遠征への送り迎えはなく、移動も自力ならば、お弁当を作ってもらえることもなかった。いつもコンビニで買ったお弁当が昼食だったし、練習を終えて家に帰っても、買ってきたお弁当やお惣菜を食べるのが当たり前だった。
泥だらけになった練習着を洗うのも自分ならば、遠征の準備をするのも自分。すべてを彼は自分でやっていた。
当時を思い出しながら、定子さんが言った。
「慎三が高校生のときは、私は仕事で出張だらけだったので、月に何回か会う程度。だから、お弁当を作ってあげたことも、ご飯を作ってあげたこともない。でも、慎三は家庭の事情を理解したうえで、何も要求することはなかった。だから、『僕ってお弁当ないの』って聞かれたことは一度もなかったんです」
ただ、それを興梠は苦とは微塵も思っていなかった。
「僕自身、親が熱心になりすぎること自体が、あまり好きではなかった。確かに遠征のときなどは、みんな送り迎えをしてもらったり、お弁当を作ってもらったりしていましたけど、電車が通っていて始発で間に合うなら始発で行けばいいし、始発で間に合わなければタクシーで行けばいい。お弁当も買っていけばよかった。
父は自営業だったし、母も仕事で全国を飛び回っていたので、自分にできることは自分でやろうと。それは、決して親が僕に無関心だったわけではなく、家族を養っていくために、必死で働いてくれていると、小さいときから思って背中を見ていたので」
鵬翔高校での活動を終えたチームの卒団式では、選手一人ひとりが親への感謝を言葉にした。
「毎日、送り迎えと、お弁当を作ってくれてありがとうございました」
「いつも試合の応援に来てくれてありがとうございました」
多忙な合間を縫って、式に参加した定子さんは、何もできなかった自分を省みて、胸が締めつけられる思いだった。
「慎三は何を言うのだろうか。みんなの前で言える言葉があるのだろうか……」
順番になり、前に出た興梠は言った。
「お弁当も作ってもらえなかったし、ご飯も作ってもらえなかったけど、うちにはうちのやり方がある。だから、誰が何と言おうと、俺はうちのやり方が一番いいし、それで幸せです」
思いがけない言葉に、涙をこぼしながら定子さんは思った。
「ありがとう。親が子どもに助けられてどうするのよ……」
興梠は言う。
「ほとんど覚えてないですね。そういうことは言ったかもしれないな、くらい。僕にとっては、すべて当たり前のことだと思っていたから、きっと覚えていないんでしょうね」
定子さんは、息子がプロサッカー選手を意識しはじめたことを、はっきりと覚えている。鵬翔高校で頭角を現して全国大会に出場し、Jリーグのスカウトたちが注目するようになった時期だった。
その日も出張から帰り、久々に息子と顔を合わせていた。
「サッカー頑張ってる?」
「頑張ってるよ」
すると、興梠は言った。
「母さん、勝負しようぜ。母さんが今、仕事で目標にしている昇格を達成するのが先か、俺がプロになるのが先か。どっちが早いか競争しようよ」
定子さんは「いいね。どっちが先かね」と答えつつも、息子が初めて発した「プロ」という言葉に決意を感じていた。
「慎三のほうが早かったんですけどね。鹿島アントラーズに入ることが決まって、私は『やられたな』って思いました。でも、そのあと、すぐに私も昇格することができて、記念のパーティーに慎三も来てくれて、みんなの前で話もしてくれて、あれはものすごく感動しました」
そのことは興梠も覚えていた。
「間違いなく母のほうが難しいミッションだったと思います。本当に仕事が大変そうで、あちこち飛び回っているから、ほとんど家にいなかったんですけど、そんな母のことをすごいなって思っていた。だって、母の仕事仲間に会うと、必ず母のことを『尊敬している』とか『慎三くんのお母さんはすごいのよ』って言われていた。それがいつも誇らしかった」
周りだけでなく、親子である2人も互いに尊敬し合っていた。
キャリアの一歩として鹿島を選んだときも、母は息子をリスペクトした。
「何で鹿島にしたの?」
全国区になっていた興梠には、複数のクラブから獲得の打診があった。交渉の場に同席すると、中には甘い言葉を囁くクラブもあった。そのなかで唯一、鹿島だけが「すぐに試合に出るのは難しい」「試合に出るまで5年は覚悟してほしい」という厳しい言葉を伝えていた。
すると興梠はサラッと答えた。
「だって、鹿島ってすごい選手たちの集まりなんだよ。その鹿島で通用できなかったら、この先、自分はプロとしてやっていけないと思ったから」
定子さんはその言葉に息子の強さを見ていた。
「すごいなと思って。そのとき親ながら、この子は厳しいほうを選ぶんだなって思ったんです。小学生のときもそうですけど、ずっと厳しい選択をして、ここまでやってきたんだなと思って。それが今の結果にもつながっているんだと感じています」
言葉だけでなく、表情でもその決意や覚悟を感じ取っていた。それは、浦和レッズに加入した2013年も——。
「私はサッカーに詳しくないので、鹿島から浦和レッズに移籍することがどんなに大変なことか、全然、知らなかった。本人は『今、ちょっと悩んでいて、浦和レッズに移籍しようと思っている』と」
悩みを打ち明けることのなかった息子が、初めて頼ってくれている。その思いに応えたかった。
「親として、ご飯を作ったりすることはできなかったけど、子どもが迷ったり、悩んだりしているときには、前に進むための言葉を持っておきたいなと思っていたんです」
だから、定子さんは背中を押した。
「いいんじゃない。サッカー選手としての人生は長くはないんだから、自分を必要としてくれるところでやってもいいんじゃないかな。自分の悔いが残らない選択をすることが、自分の人生にとっては大事なんじゃない。まあ、最後は自分が決めることだけどね」
その覚悟と決意の重さは、当時・宮崎県で行われていたシーズン前のキャンプを見に行き、再会した息子の姿を見て感じ取っていた。
「今まで見たことがないくらい、痩せていたんですよね。それだけ周りに認められるために、必死にやっていたんだなって」
少し会話をすれば、少し表情を見れば、心のうちも思いも決意も覚悟もわかるのは、「産んだだけ」と言いつつも、やっぱり母だからだ——。
「サッカーと言えば浦和レッズだ、っていつもあの子は言っていました。まち全体の熱がすごくて、宮崎まで訪ねてきてくれるファン・サポーターもいますからね。浦和レッズにはそういうエネルギーを生み、雰囲気を作り出す力をものすごく感じるので、その浦和レッズでプレーできたことは、慎三にとってよかったんだと思います。」
 エネルギー、そして熱気にあふれる雰囲気を生むファン・サポーター
エネルギー、そして熱気にあふれる雰囲気を生むファン・サポーター
そんな母にとって、興梠慎三というサッカー選手はどう映っていたのか。
「どちらかというと、あの子は自分が目立ちたいタイプではないんです。だから、自分が点を取って目立つというよりも、チームが勝つために自分が点を取っていたんだと思います。FWになってからは、自分が点を入れないと、チームが勝てないと考えたからだと思っていて……」
母の言うように、そう思いながら決めた浦和レッズでのJ1リーグ114得点だった。
興梠にも聞いた。母はどんな存在なのかと。
「繰り返しになりますけど、母の言うとおりで、本当に何もしてくれなかった。練習で泥だらけのユニフォームや練習着も普通だったら、母が洗って干してくれるはずなのに自分で洗っていたし、朝も起こしてくれるはずなのに、自分で起きて練習に行っていた。何もかも、自分でやっていたんですよ。
でもね。学生時代はスパイクも高くて、なかなか買えないものが買えていたのも、母が興梠家を支えてくれていたから。その頑張っている姿をずっと見ていたので、本当に尊敬しています。
(母と一緒に)仕事をしている人たちが、母みたいになりたいと言っているのを聞いて、自分もそういう人間になりたいなと思っていました」
浦和レッズで、チームメート、ファン・サポーターから愛される彼は、そうなっていたのではないか。

しかし、興梠は首を横に振った。
「少しは近づけたのかもしれないですけど、母にあって、僕にないのは、母はものすごく努力をする人でした。自分にはそこが、まだまだ足りなかった。選手として母に追いつくことはできなかったと思うので、これから先の人生で、少しでも近づけたらと思います」
追いかけていたのは、母の背中だった。だから、興梠は走り続けていたし、走り続けられたのだ。
12月8日、興梠慎三は選手としての旅を終える。今度は指導者として、その背中を追い続ける。
(文・原田大輔)
COLUMN

最後のポートレート

いったいこれから誰に頼ればいいんだろうか?
4ヵ月前、埼玉スタジアムで開かれた興梠慎三の引退会見、控え室でスーツに着替える興梠慎三の姿を写真に撮りながら、僕が考えていたのはそのことだった。
ゴールを決めた数はJリーグ歴代2位、ACLでの日本人最多得点、興梠慎三がこれまでに浦和レッズとともに残してきた数字は、彼の偉大さを雄弁に物語っている。
けれど、数字には残っていないプレーにこそ実は興梠慎三の本当のすごさがあるような気もする。
いつのシーズンだったか。僕はある試合で90分間、ファインダーの中で興梠慎三だけを追い続けたことがあるけれど、あれはとても興味深い体験だった。たとえば彼が前線でパスを受けた後のタメる時間だったりとか、相手DFを引きつけるためのフリーランとか、あるいは何気なく逆サイドへさばく簡単そうに見えるパスだったりとか。
(あと一試合しか残っていないし、彼が出場するかどうかもわからないけれど、もし出たらそんな見方をするのもいいかもです)
とにかく、興梠慎三という存在は僕たちにとっては、いつも困ったときになんとかしてくれる男、だったし、きっと相手にとっては、いつもなんかされそうなやつ、だったんじゃないかと思う。
そんな男がいなくなるのはやっぱり困るから、僕は記者会見当日、埼スタの控え室でネクタイを結び直す彼に向かってもう一度だけ聞いてみた。
「やっぱり、やめるのはやめようとか、そういう気持ちはないの?」と。
「ない、ない、ない!」
興梠慎三はいつものようににこりと笑うと、ジャケットに腕を通し、会見場へと続く廊下を歩き始めた。そっか、やっぱそうだよな。いくら興梠慎三といえども、永遠にサッカーを続けられるわけじゃない。

2024年12月3日、その日はシーズン最後の公開練習日だった。僕はさいたま新都心駅で電車を降りると、けやき広場を抜けて大原の練習場までの道を歩き始める。時刻は午前9時、アスファルトには秋の終わりというより、春の初めのような暖かな眩しい光がさしていて、あゝ、今から2024年シーズンが始まればいいのに、と心から思う。(あんま結果は変わんないか)
実を言うと、引退する前の興梠慎三のポートレートは、その数日前に撮らせてもらってはいた。試合用のユニフォームを着て、赤い背景紙の前で。でもいつもと同様、この人の写真を撮るのは難しかった。なぜなら興梠慎三はいつも同じ顔しかしないから。別に表情がないわけじゃない。かっこつけてくれとこちらが頼めば、かっこいい顔をしてくれる。笑ってくれといえば、笑ってくれる。(入団してしばらくは、あまりうまく笑えなかったから、そこは大きな進歩だ)
でも毎回そこには同じ興梠慎三しか写らない。なぜなら、彼には表裏がないから。
練習は9時半過ぎに始まった。まず全員で軽いジョギングがあり、そのあとにインターバルトレーニングが続いた。平日にも関わらず、シーズン最後の練習、というよりはきっと興梠慎三と宇賀神友弥の最後の練習を一目見ようと集まったファンで、スタンドは満席だった。僕は客席とグラウンドを隔てるネットの前に腰を下ろし、レンズを構え、そして少しだけミシャのことを思い出す。

シンゾー!シンゾー!あの頃はいつ練習をのぞいても、グラウンドの真ん中に置いた箱の上に腰掛けたミハイロ・ペトロヴィッチ監督が何度も彼の名前を呼んで、そのポジショニングや動き方に注文をつけていた。
この人とサッカーがやりたい!興梠慎三に鹿島アントラーズから宿敵浦和レッズに移籍する決断と勇気を与えたのは、この旧・ユーゴスラビア生まれの名将の存在だったと聞いたことがある。そして1年間ではあるけれど、彼が浦和を離れて札幌で過ごしたのもまたミシャの存在があったからだ。
ファン・サポーターの視線を浴びながら、興梠慎三はいつものように大粒の汗をかきながら、一つひとつのメニューをさぼることなくこなしてゆく。インターバルの後はロンド(ボール回し)を10分ほどやって、その後はほぼフルコートを使ったゲームが始まる。


興梠は一方のチームのトップのポジションに入る。そのなんとも形容し難い、彼独特の緩急をつけた動きを見ていると、やっぱりまだやれるんじゃないの、と思ってしまうが、これももう本人の中で答えは出ている。4ヵ月前の会見で彼は明言した。もう自分にはチームを勝たせられるだけの力がない、と。それはきっと事実だろうし、彼にまだ勝たせられる、と思わせるだけのチームではなかったことも、たぶん事実だ。
30分ほど続いたゲームが終わると、チームはグラウンド中央で円陣を組み、最後は手拍子で練習を終える。興梠慎三はクラブハウスに戻ってくると、額から汗を流しながらシューズを脱ぎ、ウインドブレーカーに着替え、サインや記念撮影を求めるファンの元へとまたグラウンドの方へ戻ってゆく。一人ひとりに丁寧に応対し、最後のサインを書き終え、最後の記念撮影に笑顔で応え終えたときには、すでに練習が終わってから1時間あまり過ぎていた。

ということで、しつこいけれど、これで本当に終わりなんだね。
「本当はね、自分の中では去年やめようと思ってた。ちょっと曖昧だったけど、もうこれが一番綺麗な形かなって思って。5:5、いや6:4くらいかな、やめるが6で、続けるが4くらい。でも、新シーズンに監督が代わるから、あと1年いてくれないかっていうことをチームから言われた。自分を必要としてくれるのはありがたかったから、じゃあもうこれがほんとにラスト1年だなと」
綺麗な形っていうのは?
「去年に関してはACLを獲ったということだよね。札幌から何のために戻って来たかというと、ACLの決勝があったから。最初はACLの決勝に出るとも思ってなかったんだけど。Jリーグの試合もそうで、夏くらいまでスタメンで出るってことは全然自分の中でも考えてなかった。でも、マチェイが監督1年目ってことでなかなかチームが結果出ない中、自分が出たときに勝ちが続いていった部分は、大きな仕事ができたのかなっていう気はしてた」

チームからは、ピッチ外、トレーニング中、お手本となるようなベテランが欲しいということも伝えられていた。ほんの少し前までの興梠慎三という選手は、誰かのお手本になるようなタイプではなかったような気がするけれど笑。
「それは自分でも思っているけど笑。でも、自分が一生懸命トレーニングをするだけでも効果はあると思ってた。自分はいろいろと発言するようなタイプではないけれども、鹿島時代にも言葉でというより背中で見せてくれていた先輩たちが多かったので、そういうのは自分もやっていかないといけないなと」
選手をやめた後の自分がイメージできなくて、やめるタイミングがずるずると伸びたってこともあるのだろうか?
「それもあるかもしれない。次に何をやりたいかって自分の頭の中に完璧にあれば、すんなりとやめられたかもしれないね。今もまだ、次を何していいのか、は定まってないけれど、やっぱり浦和レッズには恩返しはしたいです。これだけの大きな組織だし、環境もいいし、予算だって他のチームに比べたら断然いい。だから浦和レッズは常勝軍団、常に優勝争いをするべきチームだと、僕は思ってます。その手助け、土台作りをしたいっていう強い気持ちはありますね」
でも残念ながら、今シーズンの浦和レッズは優勝争いとは程遠いところにいて、背番号30もスタンドからピッチを眺めているしかない時間が長かった。
「上から見ていると、なんで?って思うことはたくさんあります。俺だったらこうするのにな、とか。別にこいつが悪いとか言ってるんじゃなくて、俺が結果を残してやろう!、チームのために頑張ろう!、そういう気迫があまり伝わってこない。技術うんぬんじゃないところがすごく目立っていた気がします」
でももちろんピッチ上の選手たちは勝利を追い求めて闘っているはず、それなのになぜ気迫が足りないように見えるんだろうね?
「んー、なんでだろう。そこがサッカーの不思議なとこ、難しさだよね。やってる側はもちろんやっている。でも、それが伝わって来ない。たしかに走ってるのは走ってるけど、じゃあ走るだけでいいのかっていうと、やっぱ考えながら走んないといけないし。今はデータとか取るけど、14キロ走っても負けたらその走りは無駄になる。だったら8キロでいいから考えて走って勝った方がいい。ちょっと目立ったからいい、じゃなくて、結果を出さないといけない。そこに貪欲なやつがいないのかな」
試合中だけでなく、練習中も声が少ない、そこもすごく引っかかる点だ。ハイプレスをかける練習をするけれど、後ろからはまったく声が出ない。みんなどこでGoをかけるのか。一人二人は行くけれど、全体がついて来ない、そういうシーンも多くあった。興梠や宇賀神、ベテランは声の重要さを伝えるけれど、結局大きな声を出して味方を動かそうとする選手は現れなかった。
「そういう細かいところ、技術うんぬんとかじゃないところです。…あとは、すごくみんな真面目。もちろん監督がいうことは絶対なんだけど、プラスアルファやっぱり自分の色を出さないといけないと俺は思ってます。監督は守備を求めるけども、選手は攻撃が得意なやつが多いんです。だから、監督が求める守備を100パーセントやっていると攻撃に力が出ない。守備を100で頑張るんじゃなく、70パーセントでさぼるところはうまくサボって、奪おうと思うんじゃなくて、限定するだけでいいんですよ。そしたら後ろは取れるから」
興梠慎三は意外と監督に向いているのかもしれないね。
「ミシャが監督のときはそんな思わなかったですけど、監督が変わっていって、なかなか試合に勝てない。じゃあ、なんで試合に勝てないんだって自分なりに考えたときに、こうしてこうしたら簡単にはがせて攻撃にいけるのに、なんでこうしないんだろうとかね。監督の戦術に不満を漏らすとかじゃなく、自分の頭の中で、なんでこういうことができないんだろうなって思うことが増えてきて。そこで、あ、監督業やりたいなって、どんどんどんどん思って来たって感じです」
スタンドから見ていると、ピッチ上だけじゃなくサポーターの見え方も変わったでしょ?
「ピッチにいると、声援ってあんまりガアーって聞こえないけど、スタンドにいるとすごい迫力がある。ゴールのときはもちろん盛り上がるんだけど、一つひとつのいいプレーでもウォーってなるし、やっぱりサポーターって見る目あるんだなって思います」
37節を終えて、浦和レッズの順位は上から数えて十二番目。いくらなんでもこの順位は、あのスタンドで声を枯らす人たちにとって酷過ぎるんじゃないかと、僕はあと一試合でピッチを去る偉大な選手に愚痴をこぼしてみる。

「いいときも悪いときも本当に全力で応援してくれて。浦和レッズっていったらやっぱりサポーター。本当にサポーターのおかげでこの浦和レッズは成り立ってるなってつくづく思うんです。だからこそやっぱり僕はサポーターにタイトルを、って思いでここまでやってきたので。結局Jリーグのタイトルは獲れなかったけど、若い選手たちにはそのタイトルを獲ってもらって、この人たちに僕ができなかったプレゼントをして欲しいなと思います」
じゃあそろそろ次があるので。クラブスタッフの声がかかり、興梠慎三は席を立つ。ラストゲームまで残るはあと4日、そして興梠慎三に話を聞きたい人はまだまだたくさんいる。
さっきまで彼が座っていた椅子を眺めながら、僕はもう一度同じことを考える。
いったいこれからは誰を頼りにすればいいんだろう?
あるいは、頼れる漢がいなくなる今こそ、浦和レッズというクラブがもう一度自分を見直すいい機会なのかもしれない。
(文/写真・近藤 篤)
COLUMN

興梠慎三のラストイヤー
興梠慎三の現役ラストイヤーが終わった。得点に関する数々の記録を持ち、現役時代に多くのタイトルを奪取し、浦和レッズの歴代レジェンドの中でも強いインパクトを残した選手の最後のシーズンに立ち会えた我々は幸せだと思う。
昨季2023シーズンはJリーグ29試合に出場し、うち15試合に先発。二桁こそならなかったが4得点した。自身二度目のACL制覇につながるゴールも挙げた。札幌に期限付き移籍する前の2021年は1得点だったことを思えば、ストライカーとしての復活の兆しを思わせた。
気がかりだったのはシーズン終盤になるにつれ、出場が減ってきたことだったが、その気がかりは今季、早い時期に払拭された。沖縄キャンプでの練習試合では、チアゴ サンタナに先発を譲ることが多くても必ず交代の一番手だったし、先発することもあった。

そして今季はJリーグ開幕戦と第2節で途中出場すると、第3節で先発。そして続けて先発した湘南戦では前田直輝の右クロスに合わせてシーズン初ゴールを決めた。
また湘南かよ。
興梠といえば『仙台キラー』として有名だが、僕は湘南の方が印象に残っている。
レッズ移籍初ゴールが2013年4月14日、J1リーグ第6節のホーム湘南戦だったことは有名だが、それ以外に2015年のJ1リーグ開幕戦と2020年の同開幕戦も湘南で、いずれもゴールを決めている。そして今季と、ゴール数では仙台戦の方が多いが、レッズで過ごした11年のうち、湘南戦で自身のシーズン初ゴールを挙げたことが4回あるのだ。ストライカーにとって、シーズン初ゴールはケチャップ瓶の封を切るようなものかもしれない。本人も「湘南からも多く取っているイメージはある」と言っていたが、それはシーズン初ゴールが多いせいではないか。ちなみに「俺は"ケチャップ理論"には賛同しない」とも言っていた。
だが、湘南戦で今季初ゴールを決めたものの、その後出番は減り、先発出場はルヴァンカップ長崎戦だけ。さらにメンバー外へと、だんだん公式戦のピッチから遠ざかって行った。復帰戦と2ゴール目はいつだろうと思っているうちに、7月29日、クラブからメールが来た。
「所属選手に関するクラブからの重要なお知らせがあり、7月31日(水)14時より、埼玉スタジアムで記者会見を実施させていただきます」

間抜けにも僕は、これが興梠の引退会見だと、最初は考えもしなかった。何だろう。まさか、誰か不祥事でも…とバカな想像さえしてしまった。
これが10月とか11月のシーズンも終わりに近づいたころなら、思い付いただろう。3年前の阿部勇樹の場合は11月14日、レッズがアジアを初制覇した日だった。興梠の引退記者会見だと聞いた後も、疑問は残った。なぜ、こんな早い時期に?
あまり選手の誕生日を知らない僕は、記者会見の当日まで、そのことに気が付かなかった。だから真っ先に質問の手を上げて、お決まりの「引退を決意した理由」と最大の疑問「なぜ、この日の発表になったのか」を尋ねた。
7月31日は、自身の誕生日。自分を生んでくれた母に感謝する日。引退にあたって母への感謝を表明したいから、この日にした。
何と素敵な理由だろう。
今後は「今季限りで引退を表明している」という枕詞が興梠について回る。メディアからの取材や、パートナーからの要請も増えるだろう。11月に発表すれば「引退フィーバー」は約1ヵ月だが、それが4ヵ月続くことになる。興梠の性格を考えれば、それは望むところではないはずだ。しかし、あえて7月31日に発表したことに、僕は感心していた。
数日後、興梠から「あの質問はナイスだった」と言われた。たしかに自分からは言い出しにくかったかもしれない。本当に、素朴な疑問をぶつけただけだったのだが、結果的にアシストができたのは良かった。
MDPで興梠の引退をどう扱うかは議論になった。
一つの案は、ラストデー、つまり最終節で大々的にやるということだ。だが監督はマチェイに替わっていて、来季の準備がすでに始まっていると見た方がいい。最終節は2ヵ月半後の2025シーズン開幕を楽しみにしてもらえるような内容にしたい。来季現役ではない選手の特集を大々的に組むのはそぐわないように思える。MDPはただでさえ、一時に比べてページ数が大きく減っているだけに。
また現在はオフィシャルメディアがかなり充実しており、最終節までにいろいろな特集があるだろう。それとの整合性も考えないといけない。
そのころ、雷雨で途中中止となった川崎戦の後半が11月22日に開催されることになった。元の試合、8月24日にももちろんMDPは発行されたが、この後半でも発行すべきだということになった。ある意味で急に1号増えたと言ってもいい。この号に興梠の大型特集を掲載することになった。その名も「興梠慎三~最後に聞いておきたい30のこと」。興梠の背番号が88だったら、どうしただろう?
11月。当時は、忙しかったはずだがたっぷりと取材時間をもらった。しかも初日ではとうてい終わらず2日間。合わせて1時間半ほどだった。いつもは2~3分の取材でも、とりあえずは断る男なのに。
中身はMDP689号に書いたが、この取材時間の長さそのものに、興梠がレッズのファン・サポーターにいかに感謝しているかが表れていると感じた。ふだんから歯に衣着せぬ選手だが、このときも"素"の興梠慎三を見せてくれた。
最終節のMDPには「about興梠慎三」を掲載することにした。選手28人全員から聞きたいところだったが、付き合いの長い選手、ポジションが同じ選手の中から選抜するしかなかった。

ふだんの練習で、興梠が誰かとじっくり話しているところを見る機会があまりなかったのだが、ほとんどの選手が何らかのアドバイスをもらっていたのではないかと思う。ただ、原口元気も似たようなことを言っていたが、興梠のプレーを盗む、真似るというのは極めて難しいのではないか。「30の質問」で感じたが、他人から見たら「すごい」と感じるプレーを簡単にやってのけるし、本人がそれを特別なことと考えていないフシがある。多くの素晴らしいFWが、それぞれ独自の特長を持っているのと同じで、興梠慎三のプレーは興梠慎三にしかできないだろう。
だが見習って欲しいプレーはある。
64分から出場した第37節・福岡戦。81分に関根からパスを受けた際、トラップが大きくなって相手に渡りそうになったが、すかさず距離を詰めてボールと相手の間に体を入れ、マイボールを守った。90分には、牲川のフィードが相手に渡りそうだと見るや、前線から猛ダッシュで戻り、ハーフウェイラインからだいぶ自陣に入った地点で敵に競り勝ちヘッドで武田につないだ。
まるで「球際で勝つとはこういうことだぞ」と、手本を見せるかのようだった。あの気持ちはチーム全員が受け継いで欲しいものだ。
少しさかのぼるが、引退記者会見で最初に述べた、引退を決意した理由。
「自分の力ではチームを勝たせられないな、と思ったのが正直な気持ちです」
認めたくはなかったし、以前の興梠とどこがどう違うのか具体的にはわからないが、点を取れなくなったのは事実だ。一つには、柏木陽介という息の合うパサーがいなくなったこともあっただろう。だが、それだけではなく、たとえばポストプレーでも、収まっていたボールが収まらなくなったと思う。
それを興梠は「チームを勝たせられない」と表現した。
僕が「レッズ歴代最多の114得点」「9年連続二桁ゴール」「18年連続ゴール」「通算歴代2位の168得点」「ACL日本人最多の27得点」という数々の記録のうち、どれが一番気に入っているかという質問をしかけたとき、「自分の記録はどうでもいい。チームが勝つことだけ考えてきた」と答えたのと、全く同じスタンスだろう。

最終節・新潟戦でも、以前なら少なくともシュートは打っていたはず、というシーンがあった。たとえば16分に関根のスルーパスをゴール前に走り込んで受けた場面だ。自分の体が数年前とは違うことを一番感じていたのは興梠自身だろう。しかし、無理をしても何とか点を取ろうと、63分に交代するまで、全力を尽くしてくれた。それは自分の花道を飾るためではなく、浦和レッズが勝利でシーズンを締めくくるため。5万人を超えるファン・サポーターと喜びを分ちあうためだ。
選手が、他人に言われる前に引退を決意するときの心境は、相当に辛い、そして固い意志があるのだと思う。にもかかわらず、チームのためにできることをやろうと、若い選手たちに振る舞いを見せ続けてくれた。今季も早い時期にゴールを挙げ、チームとファン・サポーターに喜びをもたらしてくれた。最後の最後まで一緒に闘ってくれた。そして多くの選手の気持ちを代弁して、今季の天皇杯出場資格はく奪についても言及してくれた。
在籍期間、のべ11シーズンというのは、それほど長い方とは言えない。だが、その11年間は非常に濃いものだった。最後の2024シーズンは決してフェイドアウトではなく、より多彩だったと思う。
11年間、興梠慎三を近くで見てこられたことを光栄に思う。そして来季から、有言実行ぶりを発揮してくれることを祈る。
(文・清尾 淳)